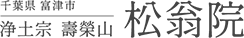最近は葬儀形式が多様化しており、どの形式が主流か分かりにくいと感じる方もいるかもしれません。
そこで、今回は最近の葬儀事情を踏まえながら、葬儀の移り変わりを解説したいと思います。
◇葬儀の歴史
鎌倉時代に広まった火葬文化は、一転して江戸時代には土葬が主流となりました。
これは、煙や臭いの問題や輪廻転生の考え方が背景にあるとされています。
その後、明治初期には「自葬祭」が禁止され、葬儀は宗教者が執り行うようになり、火葬も一時禁止されましたが、土葬用地の不足や火葬希望の声を受け、禁止令は2年後に解除されました。
また、明治時代以降、お墓は個人から家ごとのものへと変わり、「先祖代々の墓」が誕生します。
◇現在の葬儀の形
近年では、通夜・葬儀・告別式を行い、火葬後にご遺骨を骨壺に入れて先祖代々のお墓に埋葬するのが一般的でした。
しかし、現在はライフスタイルや価値観の多様化に伴い、お葬式や埋葬方法への考え方が変化しています。
最近では、家族葬や直葬が増え、一般葬は減少しています。
これは、高齢化や経済状況の変化により、近親者だけで葬儀を行いたいというニーズが高まっているためです。
松翁院では、枕経から通夜、葬儀、初七日まで一連のご対応いたします。
ご依頼に応じて、ホールや葬祭場でのご葬儀にも出向きますので、お気軽にご相談ください。
お問合せはこちら https://www.shoouin.com/contact/