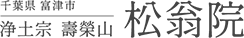従来のお墓は「その地域に住み続ける」ことを前提としていました。
しかし、昭和の高度経済成長期には生活拠点が安定していたため、少し遠くても先祖代々のお墓が受け継がれ、子や孫などの親族が管理するのが一般的でした。
ところが、少子化や核家族化の進行に伴い、お墓の在り方も変わりつつあります。
近年では、永代供養墓を選ぶ人が増えています。
◇そもそも、永代供養とは
永代供養墓は、親族に代わり寺院や霊園が供養と管理を行うお墓の形態です。
従来は、子や家族へのお墓の継承を前提としていないため、身寄りのない方や後継ぎのいない方の供養手段として利用されてきました。
また、費用面で墓石を建てられない家庭の選択肢にもなっています。
近年では、「子供に墓守の負担をかけたくない」「お墓よりもお金を遺してあげたい」といった理由で、自ら永代供養を選ぶ人も増えています。
◇「永代使用料」との違い
「永代使用料」とは墓地の使用権を得るための費用で、土地代にあたります。
ただし、これは「所有権」ではなく「使用権」に対する支払いであり、土地を購入したことにはなりません。
松翁院は室町時代後期に梵蓮社行誉上人が開山し、幕末には会津藩・白河藩の菩提所となりました。
東京湾近くの自然豊かな立地にあり、海が近い景観の良い環境で故人の供養を行っています。
お問合せはこちら https://www.shoouin.com/contact/